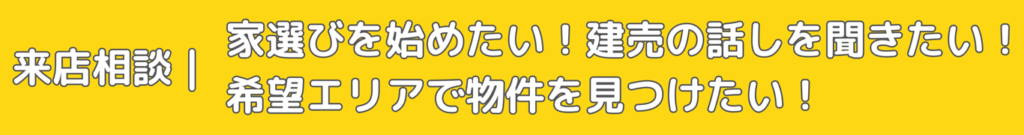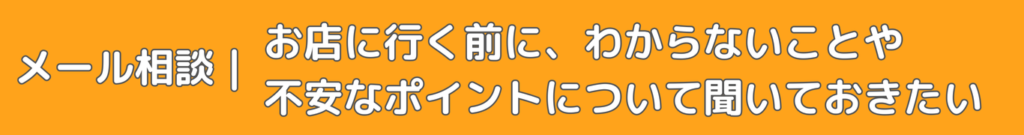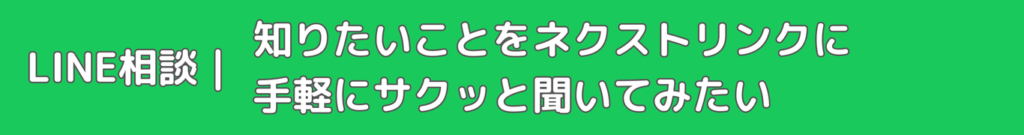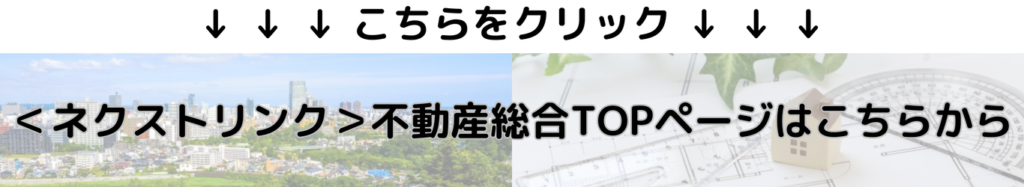COLUMN
コラム
建売住宅の売れ残りは買って大丈夫?|ハウスビルダーの元社員が徹底解説

「あの建売住宅まだ売れないんだ…」
「これだけ売れてないなら何か問題があるのでしょう?」
「そんな売れ残りの建売をでも買って大丈夫なのかな?」
建売住宅の購入を検討し物件を探し始めると、完成してから時間の経った物件に出会うことがあります。
「この物件は売れ残りなんだろう」と感じてしまうと、問題があるから売れないのでは?と考えてしまいますね。
でも売れ残りを購入するメリットや注意点をわかっていたら、自分たちにとってはその建売住宅がベストな場合があるかもしれません。
このコラムでは、建売住宅が売れ残る理由を紹介しながら、購入を考えるときに検討すべきポイントを幅広く解説していきます。
コラムを最後まで読んでいただくと、売れ残りの建売住宅に見えても「自分たちには魅力的な物件かもしれない」、と判断できるようになります。
マイホーム探しをする中で、「売れ残りだから」と偏った見方にならずに、自分たちに最も満足な家を手に入れたい方は、ぜひご覧ください。
目次
建売住宅が売れ残ってしまう理由

販売価格が物件の魅力と見合っていないケース
建売住宅の販売価格で、売れ残りが出やすい理由のなかで特に多いのは「周辺の物件価格と比べて割高」であることです。
土地の条件がよいことや建物のグレードが高ければ販売価格も上がりますが、周りの建売と比べても差がないのに価格が高い場合ですね。
複数区画で分譲されていて全く売れていないときは、この理由が当てはまるでしょう。
つぎに、ひとつの分譲地のなかでも価格が高い区画です。
角地や南道路などは人気のでる物件ですから、ほかの区画に比べて価格設定の高い場合が多いですが、割高感が先行して売れ残るときがあります。
条件のよさそうな区画ばかりが残っているときは、この可能性が高いでしょう。
最後は価格設定が的外れに高い物件です。
住宅価格にはある程度の相場がありますが、売主の安易な価格設定や原価上昇で価格を上げざるを得なくなったケースなど、明らかに価格が高い物件です。
価格で売れ残っている場合は、値引き交渉や売主の値下げによって納得のできる価格になるのであれば、購入者としても損はないでしょう。
土地の条件や立地などの問題によっても売れ残る
土地に関するマイナスポイントが理由で、売れ残ってしまう場合もあります。
はじめに土地自体に問題がある場合です。
不整形な土地や「旗竿地」のような出入口が細長い土地、また道路が狭く車の出し入れに難があるなどで売れないことがありますから、土地の条件をよく確認してみましょう。
つぎに立地がよくないときです。
公共交通機関などの利便性がよくないことや、周辺の買い物施設が少ないまたは遠いなど、また小学校の距離が遠いと敬遠されることも多いですから、立地条件にも目を向けてください。
そして周辺環境に問題がある場合です。
交通量の多い道路や工場などがあり騒音や臭いのする場所、また周りが高層の建物ばかりで陽当たりが悪いなどが考えられるので、これは現地で確認するとよいでしょう。
最後に土地にリスクがあるときです。
周辺が災害リスクの高いエリアであると、安全・安心の面で避けられる場合が多くなります。
このような土地に問題があるケースで売れ残ることがあります。
建物の企画が良くなかったことも売れ残る理由
建物や間取りなどに何らかのマイナスポイントを抱えていると、売れ残る理由となっている場合もあります。
建売住宅は万人受けするように考えられていることが多いですが、使いにくさの目立つ間取りや外観デザインの印象が悪くて、避けられてしまうこともあります。
はじめに、多くの方の生活スタイルに合わない間取りです。
家の中の動線が不自由な間取りや一見して陽当りのよくない間取り、子供部屋にするには小さい部屋ばかりであることや限られた収納しかないことなど、これから送りたい生活スタイルが叶えられない間取りは敬遠されてしまいます。
つぎに周囲の住宅と比べて特殊な間取りです。
周りは2階建ての住宅ばかりのなかにポツンとある3階建てや、4LDKの住宅が多い地域のなかにある3LDKの間取り、また個性的すぎる間取りなども避けられる傾向にあるでしょう。
最後に外観デザインです。
間取りが不整形なばかりに外観の見栄えが悪くなる建物や、色合いの全く違う外壁の組み合わせ、周りの住宅と調和のとれていない個性的な外観なども好みが分かれるので、売れない場合がでてきます。
このような建物に関する問題があって売れ残ってしまうケースもあるでしょう。
需要と供給のバランスが崩れて売れ残ることがある
欲しい人がいるから住宅が売れるのですが、必要以上に物件が販売されれば売れ残ってしまいます。
住宅を欲しい人からすれば多くのなかから好みの物件を選ぶことができるので、価格や土地・建物の条件がよくないと思われたものは残ってしまいますね。
おなじエリアに多くの物件が販売される状況にはパターンがあります。
はじめに大規模住宅地などが開発されたときです。
注文住宅と建売住宅が入り混じって販売されるケースで、多くのメーカーやビルダーが分譲に参加していると売れ残りが発生します。
つぎに、人気のあるエリアを狙って多くのビルダーが住宅を計画したときです。
人気のあるエリアはすべてのビルダーが知っていますから、売りに出される土地を常に狙っています。
土地が売りに出されたら競争になりますから必ず買われます。
そんな訳で、同じエリア内で重なると販売戸数が増えていきますし、価格が高くなる傾向にあるのもこのケースです。
最後は、想定外に自社物件のまわりで多くの物件が販売されてしまったときです。
たまたま同じエリアで、売りに出される土地が多くなるときがあります。
今までに販売実績のあるエリアであれば、売地を買わない手はありません。
多くのビルダーが同時期に、それぞれの売地を買ったために供給数が増えてしまうのですね。
このような需要と供給のバランスが崩れたときに売れ残ることがでてきます。
建売住宅は売れ残るとどうなるの?

住宅は完成してから1年が経過すると「新築」としてではなく「未入居物件」として扱われます。
これは法律でも定義されていて、場合によっては補助金交付の対象から外れることや、税制面での優遇を受けられなくなる場合もでてきます。
このような面でも、売れ残りは魅力が落ちますから、ビルダーとしてもできるだけ早く売るために対策することが多くなってきますね。
その対策として最も多いのが「値下げ」です。
値下げされるタイミングは、会社によって異なるので一概には言えませんが、完成して2ヶ月経つくらいまでが初めての値下げの時期になるでしょう。
その後も販売が進まなければ、段階的に値下げが繰り返されることも多くなります。
そのほかの対策としては「キャンペーン」が挙げられますね。
契約特典として、様々なオプション品や家具・家電などをサービスで提供してくれる場合もあります。
値下げの状況わかりづらいですし、キャンペーン内容は表向きには告知されていないので、不動産会社に尋ねてみるとよいですよ。
建売住宅が売れていない理由を調べてみよう

売れていない理由が価格である可能性を調べる
はじめに、周辺で販売されている物件の価格を比較してみましょう。
ポータルサイトのマップ検索を活用すると比較しやすいでし、周辺の価格相場も掴みやすくなりますね。
周辺の物件価格とどれほどの差があるのか、売れている区画の有無などを調べてください。
周りの物件には売れた区画があって、その物件がすべて売れていないのであれば、価格が割高なのかもしれません。
建物の仕様やグレードが周りと変わらないのであれば、その可能性も高いでしょう。
つぎに、分譲地のなかで売れていない区画がある場合です。
条件の良さそうな区画ばかりが残っているときは、売れてしまった区画の価格と比べて割高だったのかもしれません。
反対に、周りの価格より割安なのに売れていない物件が出てくるときもあります。
すべての区画が売れていないときは、価格のほかに問題があるかもしれません。
最後の1区画であった場合は、売り切るために値下げされた可能性があります。
このようなことを参考にして、売れていない物件の価格に問題がないか調べてみてください。
土地の問題が理由で売れていない可能性を調べる
物件情報ページのなかに、全体の区画図が掲載されているものを見てみましょう。
土地の形状や道路づけなど、分譲地の概略を知ることができます。
売れていない物件の土地の形が「不整形」なものや、出入り口の細長い「旗竿地」のような区画が該当するときは、その土地の条件が問題で敬遠されている可能性が高いでしょう。
ほかに道路の幅も確認してください。
周辺の道路よりも幅が狭い場合や、道路が目の前で行き止まりになる区画などは、車の出し入れが難しく感じられて売れないことがあります。
また、立地や周辺環境に問題のあるケースも考えられます。
地図アプリを活用して、周辺の利便性や小学校までの距離などを確認してみましょう。小中学校の「学区」も物件情報ページに掲載されています。
土地の条件や、立地に問題が感じられなくて売れていないときは、現地の周辺環境に問題があるかもしれません。
その例が「音」や「臭い」ですが、この場合は現地で確認するほかに方法はありません。幹線道路や工場が近くになくても、音や臭いが気になる場所もあります。
これらのことを参考にして、土地に問題がないか調べてみてください。
建物の問題が理由で売れていない可能性を調べる
はじめに間取り図を見てみましょう。
間取り図で見ただけでも使いにくさを感じる場合や、収納が明らかに少ない間取り、小さい部屋ばかりで使い方にイメージの湧かない間取りなど。
多くのご家族にとって不向きな間取りは、建物のマイナスポイントの大きな一つです。
つぎに、建物のプラン全体も見てください。
2階建ての多い地域にある3階建てや4LDK地域のなかにある3LDKの建物、周りの物件と比べて小さい面積で企画された建物や、個性的すぎる部屋のレイアウトなど。
このようなマイナスな特徴をもつ建物も敬遠されるケースの一つです。
そして、デザインの印象が悪いばかりに売れなくなることもあります。
外観や室内の色味によっては暗いイメージを受ける場合や、独特な色調を組み合わせた外壁や壁紙、周りの住宅と調和がとれていない外観など。
物件情報ページには、完成後の外観や室内風景の画像が掲載されていますから、手軽に知ることができるでしょう。
可能であれば、陽当たりなども含めて実際に現地を確認するとよいでしょう。
需要と供給のバランスで売れていないときもある
家を探しているお客様の数を超えて物件が販売されれば、需要と供給のバランスがくずれて売れなくなります。
家が欲しいと思うタイミングはご家族それぞれですから、需要が集中することがほとんど無いからですね。
たとえば、大規模な開発分譲地が販売され始めたとしても、すぐに完売することは滅多にありません。
長い期間をかけて徐々に売れていきますので、一概に売れ残りの判断はできませんね。
また建売住宅にはよくあるのですが、分譲地の最後の1~2割は売れ残ることが少なくありません。
たとえば10区画の分譲地があって、順番に売れていった最後の1~2区画になると、売れ行きが止まることがあります。
同じタイミングで家を購入する方が、ぴったり10組いないことの方がほとんどです。
そして人気のあるエリアなどでも、販売物件が重なったときには売れ残りがでます。
ビルダーが土地を購入する段階で、競争が生まれて物件価格が高くなり、家が欲しい人にとって値ごろ感がなくなるからですね。
このような、需要と供給のバランスの兼ね合いで売れていないこともあるので、住宅に問題があるのでは?と決めつかないようにしましょう。
売れていない建売住宅を買うメリット

値引き交渉に応じてくれる可能性が高くなる
ビルダーにとって売れ残りとなっている場合は、値引き交渉に応じてもらいやすくなるメリットがあります。
値下げをしても反響がなく、いくらなら売れるのかわからない状況にあるときに、「値引きしてくれるなら買いたい」と申し出があれば、応じてしまいたくなるからですね。
前述したとおり、完成して1年がたつ前に売りたいですから、できあがってからの時間が経った物件ほど、値引き交渉が通る可能性も高まるでしょう。
値引きが実現して購入予算を縮小できるなら住宅ローンの借り入れも少なくなり、当初見ていた予算を節約できてゆとりが生まれるでしょう。
ただし、値引き交渉は決めていた予算よりも安く購入できるからこそのメリットです。
周辺の物件価格と比較してどれほどのメリットがあるのかを慎重に検討してください。
完成してから時間のたった建物の状態を確認できる
売れていない物件の場合、完成してから時間の経過した状態を実際に確認できるのもメリットの一つです。
建物によっては、完成してすぐには表れない不具合が発生してしまう場合があるからで、「壁紙の不具合」や「設備の動作不良」などが挙げられます。
また物件には、いままでに見学に来られた方がいらっしゃいますから、床などにどうしてもキズがついてしまうことも考えられます。
購入前にしっかりチェックすることができて、引渡しの前に直してもらうことで安心して住み始めることができるでしょう。
購入を決めればすぐに入居できる
建物ができあがっていて売れていない訳ですから、購入すればすぐにでも入居できますね。
完成している建売住宅では、購入の契約をしてから早いと1ヶ月程度で引渡しを受けられますから、入居のスケジュールが計画しやすいです。
こどもさんの入学や進学、転勤があってすぐに転居する必要がある場合など、引越しの期限が決っているご家族にはうれしいポイントです。
また多忙な日常で、住宅購入に時間を取ることができないといった事情のある方にも完成している建物はオススメでしょう。
そして建物を見て実生活をイメージできますから、新しい家具・家電の購入準備などにも取りかかりやすく、新生活をスムーズにスタートできますね。
建売住宅の売れ残りを買う場合のデメリット

売れていない理由がわかりづらい場合もある
時間がたっても売れてないということは、敬遠される理由があるのでしょう。
その理由がはっきりしていて、ご自分たちが家に求める条件に問題ないのであればよいですが、もしも理由がわからないときには心理的な負担を抱えるデメリットがあります。
「なぜ誰も買わなかったのか」自分たちだけが知らない原因があるのではないか」「買うと自分たちが損するのではないか」など。
理由がはっきりわからないだけに、大きな不安を憶えることもあるでしょう。
ある分譲地で最後の1棟が残っていたとき、あと1組のお客様がたまたまいなかっただけだと、売れない理由がわからないことがあります。
単純に順番で売れていったとしていても、売れなかった「ちょっとした差」が大きな不安になるかもしれません。
完成してから1年の建売住宅は保証が心細くなる
新築住宅には法律が適用されて、家の構造の欠陥や雨漏りがあった場合には、引渡しを受けてから10年間の保証が義務付けられています。
まえに解説した通り、完成して一年を経過した住宅は「新築」ではなくなりますから、この対象から外れてしまい、保証が受けられなくなる可能性があるのは大きなデメリットですね。
たとえ好条件で住宅を手に入れることができても、家の保証が法律で守られていないのでは、これからの長い生活に不安が残ってしまいます。
ただし法律の義務がなくなるとしても、売主によっては法律と同じ保証をつけてくれることもあるので、保証条件を確認するとよいでしょう。
新築一戸建ての保証と同じであれば、お得な物件になるかもしれません。
未入居物件は新築の減税対象から外れてしまう
住宅を購入するときには様々な税金がかかります。
新築住宅には税額の減税措置があって、購入時または一定期間について納税額が優遇される制度があります。
たとえば、購入時の登記申請に必要な登録免許税、不動産取得するとかかる不動産取得税、不動産を所有しているとかかる固定資産税など。
建売住宅の売れ残り期間が1年を超えると、これらの税金にも違いが生じてきます。
また「住宅ローン控除」について同様です。
現在の税制では、新築に比べて中古住宅は借入限度額が低くなり、控除期間も短くなるために還付される金額が少なくなってしまいます。
比較する物件によっても変わるので一概には言えませんが、予算を押さえて購入したい方にはデメリットになるでしょう。
建物に傷みがあったまま引き渡されるかもしれない
建物が完成して売れていなければ、定期的に物件を管理する必要があります。
建築が終了したら、適切な管理を行っていかないとが劣化が進みやすくなるためで、人のいない建物では窓を開けることがありませんし、内見する方がいれば室内は少なからず埃などがたまります。
換気が不十分であれば、湿気によって建材や壁紙が傷む場合がありますし、埃のついた床の上を歩けばキズがつく恐れもありますね。
ビルダーにもよるのですが、完成してから長期間経過した物件を購入する場合に、契約条件として「現状有姿」つまり経年や人の出入りによる不具合は直さずに引き渡されることがあるのです。
そのため、建物にキズや傷みなどの不具合がある状態で、生活を始めなければならない場合のデメリットがあります。
売れ残りの建売住宅で購入前に押さえたい注意点

建物に不具合がないことを確認する
売れていない期間が長い建売住宅の場合、施工の品質に原因があるのかもしれません。
建物内部の品質に何かしらの問題があるかどうかは、ほとんどの方には判断が難しいですが、家を内見したときに、工事の仕上がりミスを多く見かけた場合は注意が必要でしょう。
間取りや設備などをチェックすることはもちろん大切ですが、細かい部分の仕上がりなどにも目配りを忘れないでください。
また販売中の管理が不適切だと、壁紙などは劣化が進みやすくなる可能性もありまし、完成している住宅では多くの方が内見しています。
人の出入りが多くなるだけキズもつきやすくなります。
そのため、建物のなかに許容できない不具合がないかしっかり確認しましょう。
妥協点を許容するために家選びの条件を決めておく
売れてない理由には何かしらのマイナスポイントがあり、その点を妥協する必要があるかもしれません。
マイナスポイントが明らかな物件でも、妥協できる条件であれば大きなデメリットには感じない場合もあるでしょう。
しかし、立地や周辺環境や問題があるのでは自分たちでは条件を変えられませんし、リフォームが制限される間取りであれば、部屋を作り替えながら住み続けることが難しいかもしれません。
物件を選ぶときに重視される条件には、価格や立地、間取りや機能性などさまざまですが、どの点が譲れないかは人それぞれです。
そのため、家の条件について「譲れないこと」と「妥協できること」を前もって決めておくことで、売れていない物件の購入を進めてよいか判断できるでしょう。
妥当な金額をリサーチしてから値引き交渉にのぞむ
長いあいだ売れていないからといって、値引き交渉が必ずしも通るとはかぎりません。
会社によっては値引きできない事情がある場合や、値下げをしたばかりのタイミングでは交渉も難しいでしょう。
また大幅な値引き額を、強気で交渉することもおすすめできません。
建売住宅は、常に不特定多数の方に向けて販売されていますから、値引きを受けるかの判断は、その問い合わせなどの状況によって売主が決めることになります。
そのため、物件を検討しているお客様がほかにもいる場合などは、取り合ってもらえないこともあります。
値引き交渉を考えるときは、販売価格が変更された経緯やそのタイミング、また周辺の物件価格などとも比較して、妥当と思われる金額で交渉しましょう。
そして値引き交渉を受けてくれたのに、買わないのはマナー違反ですから注意してくださいね。
値下げされた物件はすぐに売れてしまうときもある
物件価格が値下げされたときは、売主から不動産会社へすぐに告知されて、すぐに売れてしまうことも少なくありません。
不動産会社は、掲載している物件情報の価格を変更するとともに、物件を探しているお客様にも連絡するので、購入意欲が高まるときだからです。
検討していたお客様がいた場合、お得感のある物件となればすぐにでも購入を進める可能性があるでしょう。
また、値下げされた物件は多くの不動産会社が情報を公開しますから、値下げをきっかけに検討を始める方もいらっしゃいます。
値下げされるタイミングはわかりませんから、もしお目当ての物件があるのであれば値下げの動きに目を向けておきましょう。
購入に踏み切るときは、周辺の物件価格とも比較しながら慎重な判断をしてください。
建物が完成した時期を確認しておく
建物が完成して1年を経過すると「新築」ではなくなりますので、法律による10年保証が適用されません。
そのため長期間売れていない物件の場合、検討期間中に新築の対象から外れてしまう可能性があることに注意しましょう。
物件情報には、かならず新築時期が記載されていますので、完成経過日数を調べてください。
1年を経過する前に売買契約を結ぶことができれば、入居が遅れたとしても法律の対象となりますよ。
また、物件の購入を進めることになったときは、保証についての契約内容を確認するようにしましょう。
新築扱いではなくなった物件の、保証内容や期間は売主によって条件が変わりますので、購入を申し込む前にしっかり確認してください。
将来の売却や住み替えで不利になることも割ける
売れていない理由として立地や周辺環境、土地の条件や建物の間取りなどが挙げられた場合、将来の売却の際に不利になる可能性もあることを踏まえておきましょう。
何かしらの理由で家の売却が必要になったとき、まえと同じ理由で売却が進まずに価格が下がってしまったとしたら、住宅ローンとの相殺が難しくなってしまうこともあるからです。
売却後に住宅ローンが残ってしまい新しい住宅ローンが組みにくくなると、住み替えが思うように進まなくなることも考えられます。
将来的な売却や住み替えの可能性がある場合は、専門家である不動産会社に相談のうえ購入を進めてください。
売れ残りの建売住宅なのか見極めるためのまとめ
建売住宅が、売れていないのには様々な理由があります。
そのためご自分たちでもリサーチして、売れ残りの理由を判断できるとよいでしょう。
本コラムで解説した理由に、該当しないか調べてみてください。
また、売れていない建売住宅を買うにはメリットとデメリットがありますから、売れない理由と買わない理由が一致しないか、慎重に検討しましょう。
そして購入する前には、解説した注意点を参考にして手続きを進めてください。
仙台市・宮城県エリアで建売住宅を購入するならネクストリンクにご相談ください

売れていない建売住宅だけれど、気になってしょうがない物件を見つけたときは、ネクストリンクにご相談ください。
建売住宅に携わってきた元社員の目線で精査して、その物件の「良いところ」も「良くないところ」もしっかりお伝えします。
そして、お客様にとって魅力のある物件なのか、包み隠さず判断いたします。
さらに購入を進めるときは、値引き交渉の勘所を熟知している我々が粘り強く交渉してまいります。
また私たちネクストリンクは、どこよりも土地と建物に詳しい会社です!
「間取り」と「立地」に強い、建売住宅の元プランナーが物件選びをしっかりサポートいたします。
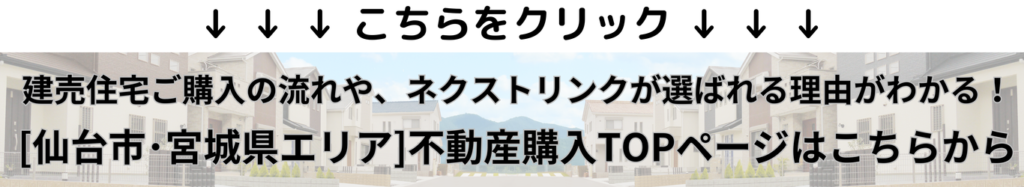
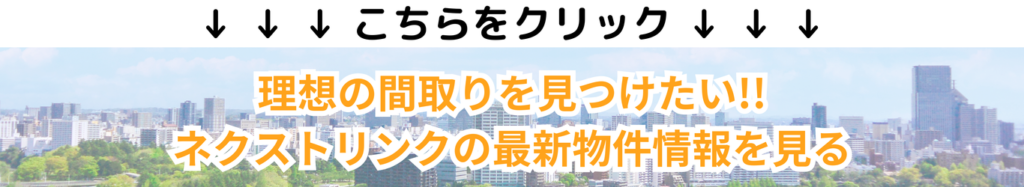
<こちらの記事も読まれています>
無料で相談できるので、気軽に活用してみてくださいね。